- HOME
- 専門診療案内
- 消化器科
吐く、下痢する、食べない…そのお悩みに
専門医が動物さんの消化器と
真摯に向き合います
- こんな症状
ありませんか? - 繰り返し吐く、吐き気が続いている
- 下痢が続いている、血便が出る、便がいつもと違う
- 食欲がない、食欲ムラがある、急に食べなくなった
- お腹が張っている、触ると痛がる、ゴロゴロ鳴る
- 体重が減った、痩せてきた
- 頻繁に草を食べる、異食行動がある
- 口臭がひどい、歯茎の色が悪い
- 白目が黄色い
これらの症状にお悩みの際は、当院にご相談ください。
動物さんが元気に過ごせるよう、専門医が全力でサポートいたします。
DOCTOR
担当医の紹介
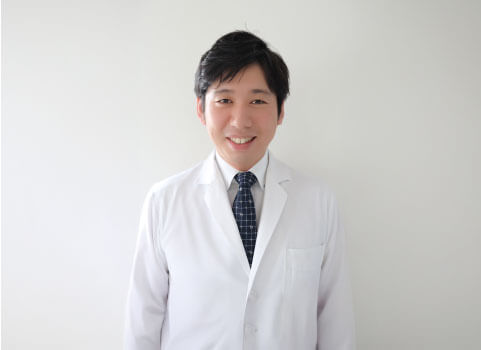
- 横浜鶴ヶ峰院 副院長
- 室 卓志
- 専門分野
-
- 腎泌尿器・生殖器科
- 消化器科
- 経歴
-
- 都内動物病院
- 日本動物高度医療センター(泌尿器生殖器科、消化器科)
- JASMINEどうぶつ総合医療センター(腎泌尿器科、消化器科)
- ハグウェル動物総合病院 横浜鶴ヶ峰院 副院長
- 所属学会
-
- 日本獣医麻酔外科学会
- 日本獣医腎泌尿器学会 認定医
- RECOVER WEBコース修了
FEATURES
ハグウェル動物総合病院‐横浜鶴ヶ峰院の3つの特徴
-
 POINT01
POINT01- 高度な画像診断と
内視鏡検査 - 単純X線検査や造影X線検査、超音波検査に加え、CT検査を活用した詳細な画像診断で、消化管や肝臓、胆嚢、膵臓などの異常を正確に把握します。また、内視鏡検査により、直接消化管内を観察し、組織を採取することで、より精密な診断と治療に繋げます。
- 高度な画像診断と
-
 POINT02
POINT02- 内科・外科の両面から
アプローチ - 食事療法や薬物療法、超音波ガイド下治療、内視鏡下治療といった内科的治療から、肝生検、胆嚢摘出、消化管内異物摘出、会陰ヘルニア整復、消化器(肝臓、胆嚢、膵臓、消化管)腫瘍切除といった外科手術まで、消化器疾患の原因と進行度に応じた最適な治療法を柔軟に選択・提供します。
- 内科・外科の両面から
-
 POINT03
POINT03- 個体ごとの食事管理・
長期的なサポート - 慢性的な消化器疾患では、食事管理が非常に重要です。個々の動物さんの体質や病状に合わせた療法食の選択、手作り食のアドバイスなど、長期的な視点での栄養管理と再発予防をきめ細やかにサポートいたします。
- 個体ごとの食事管理・

APPROACH
治療アプローチ
消化器疾患の治療は、原因が多岐にわたるため、正確な診断に基づいた多角的なアプローチが重要です。当院では、動物さんの症状、ライフスタイル、基礎疾患などを総合的に考慮し、最適な治療プランを提案します。
-
内科療法
-
- 食事療法
- 食物アレルギー、慢性腸疾患、肝疾患、胆泥症、膵炎など、多くの消化器疾患で療法食が非常に重要です。低アレルゲン食、低脂肪食、消化ケア食など、病態に合わせた食事を指導します。
- プロバイオティクス、プレバイオティクス
- 腸内環境を整えるために、乳酸菌などのプロバイオティクスや食物繊維などのプレバイオティクスを推奨することもあります。
- 薬物療法
- 吐き気止め、下痢止め、消化管の動きを改善させる薬、抗菌薬、炎症を抑える薬(ステロイドなど)、利胆剤、肝庇護薬などを症状に応じて処方します。
- 輸液療法
- 脱水や電解質異常がある場合に、点滴で水分を補給します。
- 超音波ガイド下治療
- 超音波診断装置を用いて病変を除去したり、薬物を投与したりすることで大きな負担なく治療します。
-
外科療法(手術)
-
- 肝生検
- 肝臓の病気は血液検査や画像検査だけでは判断が困難なことも多く、肝臓の一部を採取し治療方針を決める必要があります。肝臓の一部を複数箇所採取したり、胆汁を採取したり、門脈圧測定や造影を実施し、正確な診断と適切な治療に努めます。
- 胆嚢摘出術
- 胆嚢の異常により嘔吐や食欲低下、黄疸などが生じた場合、胆嚢を摘出する必要があります。胆嚢の管が詰まったり、胆嚢が破裂した場合には緊急手術が必要となることもあります。
- 消化管内異物摘出術
- 誤って飲み込んだ異物が消化管内で詰まってしまった場合など、内視鏡では取り除けないケースで手術による摘出を行います。
- 会陰ヘルニア整復術
- 筋肉などの自己組織を用いた整復法を中心に用い、排便異常を改善させます。
- 消化器(肝胆膵、消化管)腫瘍切除術
- 肝臓、膵臓、消化管などにできた腫瘍を外科的に切除します。消化管などは切除後の再建が重要となります。
-
内視鏡を用いた治療
-
- 消化管内の異物摘出、組織生検(診断のため)、ポリープ切除、バルーン拡張、ステント設置など、動物さんの負担を抑えながら行うことができます。
-
対症療法・緩和ケア
-
- 症状が重い場合や、根本治療が難しい慢性疾患、末期疾患の場合に、食欲不振や嘔吐、下痢などの症状を和らげ、動物さんの快適さを維持することを目的とします。
これらの治療法を単独で、あるいは組み合わせて、動物さんとご家族にとって
DISEASE
代表的な消化器疾患
犬の主な疾患
-
- 急性胃腸炎
- 食事の急な変更、異物誤食、ストレス、細菌・ウイルス感染などにより、急性の嘔吐や下痢を引き起こす病気です。多くは対症療法や食事管理で回復しますが、重症化することもあります。
-
- 慢性腸症(炎症性腸疾患:IBDなど)
- 慢性の下痢や嘔吐、体重減少が続く病気で、食事の影響や腸内細菌の異常、免疫介在性の炎症が関与すると考えられています。内視鏡検査が必要となることもあり、食事療法や免疫抑制剤による管理が中心となります。
-
- 胆嚢粘液嚢腫
- 胆嚢内にムチンと言われる物質が充満した状態で胆嚢の管の詰まり(胆管閉塞)や破裂(胆嚢破裂)がみられることがあり、元気食欲低下や嘔吐、黄疸などの症状がみられます。手術が必要となることが一般的です。
-
- 慢性肝炎
- 肝細胞に慢性的な炎症がみられ、黄疸が生じたり、肝機能が低下することがあります。免疫が関与していると言われており、免疫抑制剤による治療が必要となります。
-
- 膵炎
- 膵臓に炎症が起きる病気で、激しい嘔吐、腹痛、食欲不振、脱水などの症状が見られます。重症化すると命に関わることもあり、食事管理や内科的治療が重要です。
猫の主な疾患
-
- 慢性嘔吐・下痢
- 猫にも慢性の消化器症状はみられ、食物アレルギー、炎症性腸疾患(IBD)、リンパ腫など、様々な原因が考えられます。詳細な検査と慎重な治療アプローチが必要です。
-
- 毛球症
- 自分で毛づくろいをした際に飲み込んだ毛が胃腸にたまり、吐き気や食欲不振、便秘などを引き起こす病気です。日頃のブラッシングや毛球ケアフードが予防に繋がります。
-
- 便秘
- 猫は犬に比べると便秘になりやすく、原因としてストレス、水分不足、大腸の運動異常、骨盤異常、神経異常などが挙げられます。重度の便秘では嘔吐や食欲低下がみられることがあります。食事療法や薬物療法が必要で、重度の場合は手術が必要なこともあります。
-
- 肝リピドーシス(脂肪肝)
- 食欲不振が長く続いた際に、肝臓に過剰な脂肪が蓄積してしまう病気です。食欲不振が続く猫に多く、積極的な太陽療法と早期の積極的な栄養管理(強制給餌やチューブフィーディングなど)が救命に繋がります。
CASES
当院の症例紹介
-
タオルを飲み込み、激しい嘔吐が続く
ゴールデン・レトリーバー/オス(2歳)症状 誤ってタオルを飲み込んでしまい、激しい嘔吐が続く。 診断
・
治療X線検査と超音波検査で胃内にタオルを疑う構造物を確認。内視鏡により摘出。 解説 異物誤食は犬に多く見られます。早期の診断と適切な処置で、消化管の損傷を最小限に抑えられます。大型の異物や腸に流れた異物は手術での摘出が必要となることがあります。 -
慢性的な下痢・体重減少
雑種犬/メス(10歳)症状 3ヶ月以上、慢性的な下痢が続き、体重が減少している。 診断
・
治療血液検査の結果、低蛋白血症、低アルブミン血症がみられ、超音波検査で消化管粘膜の粗造や粘膜の線状高エコー像がみられた。内視鏡検査にて腸粘膜の白色点状構造物が多数みられ、内視鏡下消化管生検の結果、慢性腸炎とリンパ管拡張がみられ、リンパ管拡張症による蛋白漏出性腸症(PLE)と診断。超低脂肪食を用いた食事療法とステロイド剤の内服を開始し、低アルブミン血症は顕著に改善し、下痢も改善。 解説 リンパ管拡張症は超音波検査で診断できる場合がありますが、その原因精査のためには内視鏡検査が必要です。PLEは脂肪制限食(低脂肪食もしくは超低脂肪食)で改善する場合もありますが、ステロイド療法などの薬物療法が必要となることもあります。 -
食欲低下・激しい嘔吐・腹痛
ミニチュア・シュナウザー/オス(8歳)症状 急に元気と食欲がなくなり、激しい嘔吐と腹痛がみられ、粘膜色の黄染がみられた。 診断
・
治療血液検査で肝酵素上昇と黄疸がみられ、超音波検査で胆嚢粘液嚢腫による胆嚢破裂と診断。脱水が重度であったため入院して輸液療法を実施後、胆嚢摘出術を実施。胆嚢摘出後、黄疸は改善し、元気食欲も改善し退院。 解説 胆嚢疾患は症状が出た場合には重症化していることが多く、胆管閉塞や胆嚢破裂では早期の外科治療が必要となります。重症化している場合は亡くなる可能性もありますが、周術期を乗り越えられれば、元気に退院できることが一般的です。 -
食欲低下・嘔吐
スコティッシュフォールド/メス(12歳)症状 時々嘔吐がみられ、食欲も落ちてきた。 診断
・
治療血液検査で肝酵素上昇、超音波検査にて肝臓に腫瘤がみられた。CT検査を実施し、肝葉切除を計画。希釈式自己血輸血を実施し、肝葉切除を実施。病理組織学検査にて胆管嚢胞腺腫と診断。術後の経過は良好で一般状態は改善。 解説 肝臓腫瘍は犬猫でみられる腫瘍です。肝臓腫瘍の診断はX線検査や超音波検査でも可能ですが、転移の有無の評価や手術計画を立てるためにはCT検査が必要です。外科治療により長期的な余命が得られる可能性があります。
FLOW
治療の流れ
-

- 01受付・問診
- ご予約の上ご来院ください。現在の症状、食事内容、排便・排泄状況、既往歴など、消化器に関連する情報を詳しくお伺いします。
- ご予約について
-

- 02身体検査・臨床検査
- 全身の状態を確認し、血液検査、便検査、X線検査や超音波検査を実施します。必要に応じて細胞の検査なども実施します。
-

- 03精密検査
- 必要に応じて、当院のCT検査、消化管内視鏡検査などを実施し、病変の特定や組織の評価を行います。
-

- 04診断・治療計画の説明とご相談
- 検査結果に基づき、獣医師が病態、診断名、そして動物さんとご家族にとって最適な治療計画(上記「治療アプローチ」の内容を含む)の選択肢と、それぞれのメリット・デメリット、費用、予後について詳しくご説明し、ご相談の上決定します。
-

- 05治療開始
- 決定した治療計画に基づき、内科的治療(食事療法、薬物療法、輸液など)や外科手術を実施します。
-

- 06経過観察・治療効果の評価
- 定期的にご来院いただき、症状の改善度合いや治療効果を確認します。必要に応じて治療計画を調整し、副作用の有無も確認します。
-
- 07長期的な消化器管理
- 慢性疾患の場合は、再発予防のための食事管理、生活習慣のアドバイスなど、長期にわたるサポートを提供します。
- 専門外来の注意点
-
- 当院の消化器科専門外来は、完全予約制となっております。
- ご紹介いただく際は、これまでの症状の経過(いつから、頻度、便や嘔吐物の状態など)、既往歴、現在の内服薬、与えているフード、他院での検査データ(血液検査、超音波画像、X線画像、CT画像など)を可能な限りご持参いただけますと、スムーズな診察と診断、治療計画の立案に繋がります。
- 吐き気や下痢の症状の場合、可能であれば、嘔吐物や便の様子を写真や動画で撮影してお持ちいただくと、診察の参考になります。
- 治療に時間がかかる場合や、定期的な通院、食事管理が必要となる場合があります。
- 治療が必要と判断された場合は、事前に治療方針、費用、リスク、予後について詳細な説明を行い、ご家族と十分に話し合った上で実施いたします。
診療料金について
消化器科の診療料金は、検査内容(血液検査、X線検査、超音波検査、CT検査、内視鏡検査など)、
治療内容(手術の有無、投薬、輸液の頻度など)、使用する薬剤、入院日数などによって大きく異なります。
診察時に、それぞれの動物さんの状態に合わせた治療計画と、それに伴う概算費用を丁寧にご提示し、ご説明させていただきます。
詳細な料金については、お電話または来院時にスタッフにお気軽にお尋ねください。
FAQ
よくある質問
- 下痢や嘔吐が続いたら、すぐに病院に行くべきですか?
- はい、脱水や栄養失調に陥る危険があるため、特に子犬・子猫や高齢の動物さんの場合、早めに動物病院を受診してください。自己判断で市販薬を使用すると、かえって症状を悪化させることもあるため、獣医師の診察を受けることをお勧めします。
- 食物アレルギーの場合、どのような食事を与えれば良いですか?
- 食物アレルギーの診断にはアレルギー検査(IgE検査、リンパ球反応検査)や除去食試験が必要です。診断が確定した場合は、アレルゲンを含まない療法食を継続していただくことになります。手作り食の場合も、獣医師の指導のもとでアレルゲンを避けたレシピを作成します。
- 内視鏡検査で何が分かりますか?
- 内視鏡検査では、食道、胃、十二指腸、空腸の一部、回腸、大腸の内部を直接モニターで観察することができます。炎症や潰瘍、腫瘍などの病変を目視で確認できるだけでなく、組織の一部を採取(生検)して病理検査を行うことで、より正確な確定診断に繋げることができます。また、消化管内の異物除去やバルーン拡張術にも利用されることがあります。
- 慢性的な消化器疾患の場合、ずっと薬を飲み続ける必要がありますか?
- 慢性腸症など、一部の消化器疾患では、病気のコントロールのために長期的な投薬や食事管理が必要となる場合があります。しかし、症状が安定すれば薬の量を減らしたり、中止できるケースもあります。獣医師が定期的に状態を評価し、最適な治療計画を調整していきます。
RESERVATION
専門診療のご予約方法
-
- 飼い主様へ
- 他動物病院を受診中の場合は、かかりつけ動物病院の担当獣医師様からご予約をお願いします。
-
- 獣医師様へ
- 専門診療をご希望の動物病院様からのお申し込みは、下記予約フォームより随時受け付けています。
検査を受けられる動物さんに、検査前日の夜からの絶食(最低10時間)をお願いしています。
飲水は検査当日の朝まで可能です。
飲水は検査当日の朝まで可能です。
CONTACT
