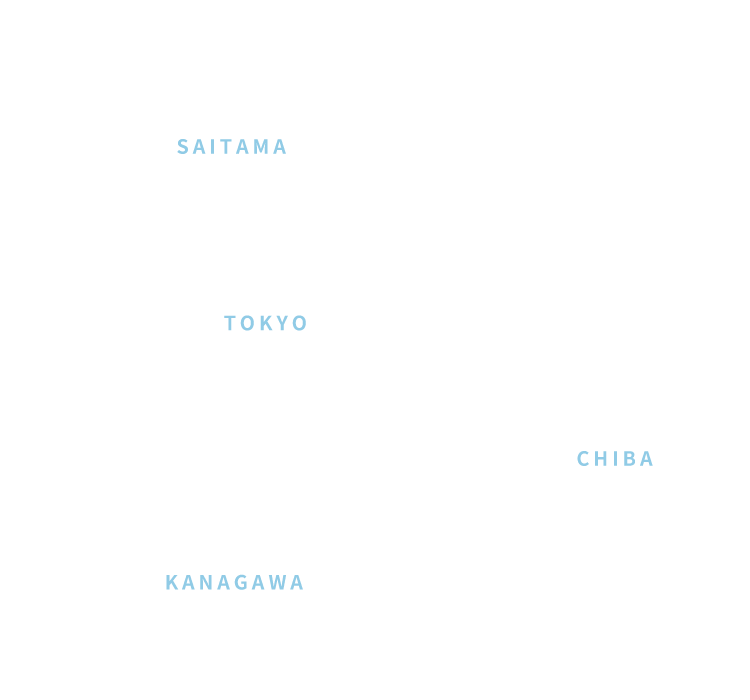- HOME
- 診療案内
- 歯科
- このようなお悩みは
ありませんか? - 口臭が強くなる
- 歯ぐきが腫れている、出血している
- 食べづらそうにしている、口を気にする
- 歯がグラグラしている、抜けてしまった
- 顔が腫れている
- 口の中にできものがある
よくある歯科の疾患
犬の主な疾患
-
- 歯周病
-
犬ではむし歯の発生はほとんど見られませんが、歯周病は非常に多い歯科疾患であり、2歳以上の犬のおよそ80%に何らかの歯周病の兆候があると言われています。歯周病の主な原因は、歯垢(プラーク)に含まれる歯周病原菌であり、歯を支える歯周組織に感染することで炎症を引き起こし、徐々に歯周組織が破壊・吸収され、最終的には歯が抜け落ちてしまう進行性の炎症性疾患です。
歯周病にかかった犬では、強い口臭や歯肉の腫れ、出血が見られ、さらに進行すると歯を支える骨の吸収が進み、歯肉の後退や歯のぐらつきが認められるようになり、最終的には歯が抜け落ちてしまいます。重度の歯周病では、以下のような合併症を引き起こすことがあります。- 【根尖性歯周炎】
歯の根元(根尖部)に炎症が起こり、膿がたまる(根尖膿瘍)歯周炎です。特に奥歯(第四前臼歯)に多く見られ、目の下が突然腫れたのち、歯肉や皮膚に穴が開き、膿や血液の排出が見られることがあります。 - 【口腔鼻腔瘻】
歯周病の悪化により、口腔(特に犬歯の部分)と鼻腔がつながってしまう病態で、鼻汁、くしゃみ、鼻出血などの症状が見られます。 - 【全身への影響】
歯周病原菌が血行性または免疫反応を介して全身に波及し、心臓・腎臓・肝臓などの臓器に悪影響を及ぼすことがあります。
歯周病の治療は、軽度であればご自宅での歯みがきなどのホームデンタルケアによる治療も可能ですが、進行している場合には全身麻酔下での歯石除去(スケーリング)と研磨(ポリッシング)が必要になります。さらに進行している場合には抜歯を行うこともあります。
いずれの場合も、治療後の継続的なホームデンタルケアが非常に重要であり、歯みがき(プラークコントロール)の可否が歯周病の進行に大きく関わってきます。定期的な口腔ケアを行うことで、愛犬の歯の健康を守り、全身の健康維持にもつなげましょう。 - 【根尖性歯周炎】
-
- 口腔内腫瘍
- 口腔内腫瘍は、犬や猫における腫瘍の中で4番目に多いと言われています。口の中に腫瘍ができると、一般的に口臭や口の中からの出血、よだれの増加、食べづらそうにする、顔が腫れるといった症状が見られことがあります。腫瘍が進行すると、食欲不振や嚥下障害、口から食事をこぼす、口を開けた時や食べる時に痛がるなどの症状が現れます。悪性腫瘍の場合、顎の骨に浸潤することや、他の臓器に転移を起こす可能性があります。犬や猫に多く見られる口腔内腫瘍には、良性のエプリスと、悪性の悪性黒色腫(メラノーマ)、扁平上皮癌、線維肉腫、および骨肉腫などがあります。悪性腫瘍では進行が非常に早いものが多いため、早期の発見と治療が非常に重要です。診断には視診や触診に加え、X線検査、CT検査、組織生検などで行います。治療は外科的切除が基本となりますが、腫瘍の種類や進行度によっては放射線治療や化学療法なども併用して行うことがあります。口腔内腫瘍は進行するまで目立たないことが多いため、「最近口臭が強い」「片側だけ食べづらそう」などの日常の変化に気づくことが、早期発見につながります。
猫の主な疾患
-
- 歯肉口内炎
- 猫の慢性歯肉口内炎は、歯肉や口の中の粘膜に強い炎症が広がる慢性的な疾患です。中年齢の猫での発症が多く、歯肉および口腔粘膜が赤く腫れる、浮腫、出血、肉芽形成、びらんなどの炎症性・潰瘍性の病変が見られます。主な症状として、よだれが出る、食事中に奇声をあげる、食べづらそうにする、性格の変化(痛みのために攻撃的になる)、よだれによる被毛の汚れ、口臭が強くなるなどの症状が見られます。強い痛みにより食事量や飲水量が減少し、脱水や体重減少などを生じ、猫のQOL(生活の質)は大きく低下してしまいます。原因については現在のところはっきりとは明らかになっていませんが、カリシウイルスなどのウイルス感染や、特定の細菌の関与、口腔内微生物に対する過剰な免疫反応など、いくつかの要因が複合的に関係していると考えられています。
診断は、視診や口腔内検査、血液検査、ウイルス検査などを行い、必要に応じて病理組織学的検査などを用いて行います。治療はウイルスや細菌などの口腔内微生物を可能な限り除去し、それに伴う炎症反応をなるべく抑える治療を行います。内科的な治療は一時的には症状が軽減しますが、再発しやすく、薬のみでは十分な改善が見られないケースが多いため、重度の歯肉口内炎の場合には全身麻酔下での抜歯が治療の中心となります。この疾患は完治が難しいケースも多く、長期的なケアと継続的な管理が大切です。
- 口の健康を守ることが、全身の
健康を守ることにつながります - 犬や猫の歯科疾患は、単に口の中だけの問題ではなく、全身の健康状態に大きな影響を与えることがあります。日頃から口臭や食べ方、表情などに注意を払い、ちょっとした変化を見逃さないことが、病気の早期発見と早期治療につながります。普段からスキンシップの一環としてお口を触ったり、デンタルケアを行うことで、異常に気づきやすくなります。普段からのスキンシップが、病気の早期発見につながります。
「最近、口が臭う気がする」「ごはんの食べ方がおかしい」「口を触らせてくれなくなった」といった違和感を感じたら、ぜひお早めにご相談ください。当院では、歯科用レントゲンを完備しており、必要に応じて歯科検診・スケーリング・抜歯・腫瘍診断などの治療を行っています。健康で快適な毎日のために、定期的な口腔ケアを一緒に続けていきましょう。
治療の流れ
-

- 01受付・問診
- ご来院いただきましたら、受付をお願いいたします。初めての場合は詳細の情報などを記入いただく初診表の記入にご協力ください。
-

- 02検査
- 問診や身体検査の結果をもとに、飼い主様との相談の上、原因特定のための検査を行います。
-

- 03診断・治療の提案
- 検査結果をもとに、獣医師が診断を下し、適切な治療法を提案します。
治療は、薬物療法、食事療法など、動物さんの状態に適した方法を選択します。治療計画は、飼い主様と詳しく相談した上で決定し、すべての選択肢とそれぞれのメリットとリスクについて説明します。
-

- 04お会計・次回予約
- 治療後、受付にてお会計を行います。この時、お薬の飲み方や次回の来院目安などをお伝えさせていただきます。
また、治療における不明点などもお気軽にお申し付けください。
- 当院に初めて来院される方は
まずはこちらをご確認ください 当グループについて