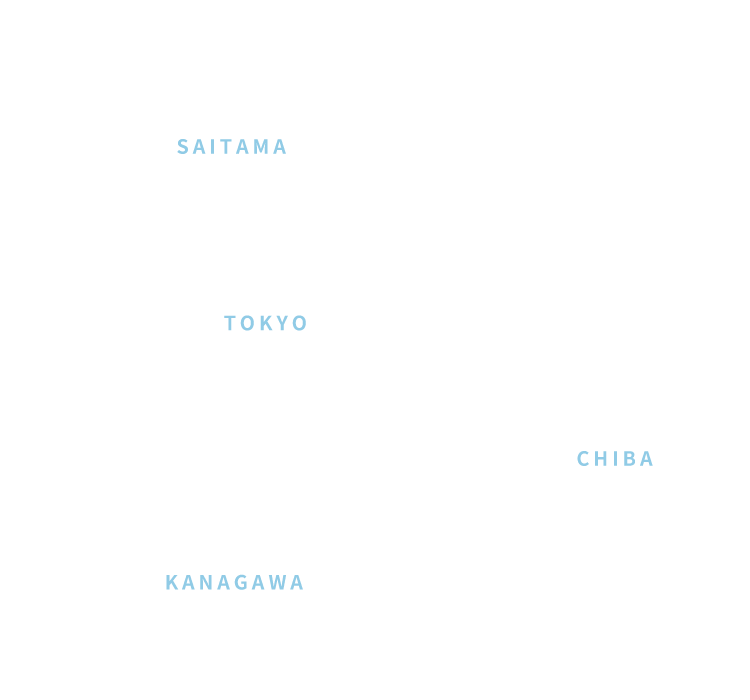- HOME
- 診療案内
- 栄養管理科
- このようなお悩みは
ありませんか? - 最近、体重が増えてきた気がする
- 尿がキラキラしている/血が混じっている
- 特定のフードを食べると下痢や皮膚のトラブルが出る
- お水をよく飲み、おしっこの量が増えてきた
- どの食事を食べさせればいいか、わからない
- 手作りフードは何をあげていいの?
よくある栄養管理科の疾患
犬・猫の主な疾患
-
- 肥満(ひまん)
- 摂取カロリーが消費エネルギーを上回ることで脂肪が蓄積し、体重が過剰になる状態です。見た目では胴回りのくびれがなくなり、動きが鈍くなったり、階段や散歩を嫌がるようになることがあります。
診断はボディコンディションスコア(BCS)などで行い、治療には低カロリーフードへの切り替えや運動量の調整が必要です。肥満は関節疾患、糖尿病、心臓病など多くの病気のリスクを高めるため、早期の対処が重要です。
-
- 尿石症(にょうせきしょう)
- 尿の中のミネラル成分が結晶化・凝集することで膀胱や尿道に石(結石)ができる病気です。血尿や頻尿、排尿時の痛み、尿が出にくいなどの症状が見られます。
尿検査や画像診断(レントゲン・超音波検査)で診断し、結石の種類に応じて食事療法を中心に、必要に応じて内科的または外科的処置を行います。再発予防のためには、水分摂取の管理と長期的な食事管理が大切です。
-
- 食物アレルギー
- 摂取した特定のたんぱく質などに対して免疫反応が起こり、皮膚症状や消化器症状が引き起こされる状態です。かゆみ、赤み、脱毛、耳のトラブル、慢性的な下痢や軟便などが主な症状です。
診断にはアレルゲン除去食を用いた食事療法(エリミネーションダイエット)が用いられ、改善が見られた場合は再現試験を行って確定診断とします。長期的にはアレルゲンを含まない療法食の継続が必要です。
-
- 下痢・嘔吐(消化器症状)
- 犬や猫の下痢や嘔吐は、消化管の一時的な不調から、感染症、食事内容の変化、慢性疾患まで幅広い原因で起こる症状です。急性のものは一時的な刺激や誤食が原因となることが多く、慢性的な場合は食物アレルギー、炎症性腸疾患(IBD)、膵炎、肝疾患などが背景にあることもあります。
診断には糞便検査、血液検査、超音波検査、食事履歴の確認などが行われ、必要に応じて内視鏡検査や食事療法の試験を行います。治療では原因に応じた食事内容の調整(低脂肪食や加水分解たんぱく食など)が重要で、薬剤と併用して回復を目指します。再発を防ぐためにも、安定した腸内環境を保つ栄養管理が欠かせません。
-
- 高脂血症(こうしけっしょう)
- 血液中の中性脂肪やコレステロールが異常に高くなる状態で、無症状のこともありますが、膵炎や脂肪腫、目の周囲に白い沈着物が現れることもあります。
血液検査による診断後、脂質を抑えた処方食や食事回数の調整によってコントロールを行います。肥満や糖尿病と併発することもあるため、総合的な栄養管理が求められます。
この他にも、糖尿病、慢性膵炎、
肝疾患、食欲不振、老齢性衰弱
などにも
食事管理を行うことが
推奨されております。
治療の流れ
-

- 01受付・問診
- ご来院いただきましたら、受付をお願いいたします。初めての場合は詳細の情報などを記入いただく初診表の記入にご協力ください。
-

- 02検査
- 問診や身体検査の結果をもとに、飼い主様との相談の上、原因特定のための検査を行います。
-

- 03診断・治療の提案
- 検査結果をもとに、獣医師が診断を下し、適切な治療法を提案します。
治療は、薬物療法、食事療法など、動物さんの状態に適した方法を選択します。治療計画は、飼い主様と詳しく相談した上で決定し、すべての選択肢とそれぞれのメリットとリスクについて説明します。
-

- 04お会計・次回予約
- 治療後、受付にてお会計を行います。この時、お薬の飲み方や次回の来院目安などをお伝えさせていただきます。
また、治療における不明点などもお気軽にお申し付けください。
- 当院に初めて来院される方は
まずはこちらをご確認ください 当グループについて