
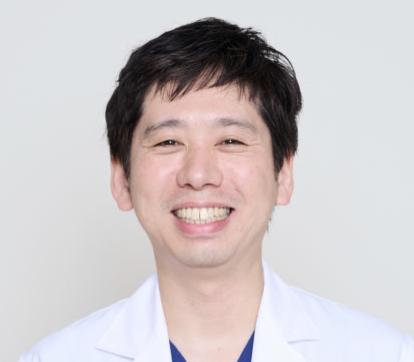
【腎泌尿器科診療】室 卓志 獣医師
【担当科目】総合診療科・腎泌尿器科・消化器科
シュウ酸カルシウム結石は犬の尿路結石症の中で高頻度に認められる疾患で、再発率が高いことが特徴です。結石形成のメカニズムやリスク因子を理解し、適切な治療と予防を行うことが獣医師に求められます。特に食事内容や生活管理が再発予防の鍵となります。
目次
1. 原因
シュウ酸カルシウム結石は、尿中のカルシウムとシュウ酸の過飽和状態により形成されます。主な因子は以下です。
-
尿の過飽和状態:カルシウムとシュウ酸が高濃度になると結晶化が促進されます。
-
尿pH:酸性〜中性尿で結石が形成されやすいと言われています
-
食事内容:高カルシウム・高シュウ酸食やビタミンC過剰摂取がリスクとなります。
-
遺伝的素因:ミニチュアシュナウザー、ヨークシャーテリアなど特定犬種に高頻度に現れます。
-
水分摂取不足:尿量が減少すると結晶形成のリスクが上昇します。
-
尿路感染症:感染に伴わないことが多いですがが、慢性炎症は形成に影響を与えます。
2. 症状
典型的な症状は以下です。
-
頻尿・排尿困難:尿の回数が増えたり、尿のポーズをする回数が増えます
-
血尿(顕微鏡的または肉眼的):尿が赤くなります
-
尿道閉塞による急性腎不全症状(特に雄犬):結石が詰まることで、尿が排出されず腎臓への負担が見られ、元気がなくなります
-
尿失禁や排尿時の痛み:尿をいたるとこでしてしまったり、尿をした後に泣き叫びます
-
食欲低下、元気消失(重度の場合):尿が出ないことが起こると、尿毒症となりぐったりすることがあります
3. 診断
診断は臨床症状に加え、検査で確定します。
-
尿検査:結晶の形態(八面体、三角柱)、尿pH、潜血、細菌の有無を確認します。
-
画像診断:レントゲンで不透過性結石を確認します。超音波で尿路拡張や結石位置を評価します。
-
尿培養:感染症の有無を確認します。
-
血液検査:腎機能を評価します。
4. 治療
シュウ酸カルシウム尿石症は溶解療法が難しいため、以下の治療が中心です。
-
外科的摘出:膀胱内、さらには尿管などに結石が見られた場合は、外科手術によって結石を取り除きます。
- 水分摂取促進:輸液や飲水で尿量を増やし結晶への対応を行います。
-
食事療法:シュウ酸・カルシウム含量の調整、尿pHコントロールを行います。
-
抗菌薬:尿路感染がある場合のみ投薬いたします。
5. 食事管理とリスク食材
シュウ酸カルシウム結石の再発防止には食事管理が非常に重要です。特に以下の食材は注意が必要です。
高シュウ酸食材
シュウ酸が尿中でカルシウムと結合しやすく結石リスクを高めます。
-
野菜:ほうれん草、ビーツ、スイートポテト、ルバーブなど
-
豆類:そら豆、落花生、豆腐(加工度により変動)など
-
穀物:大麦、ライ麦、小麦ふすまなど
-
加工品:ナッツ類
高カルシウム食材
尿中カルシウムを上げ、結石形成の一因となります。
-
乳製品:チーズ、ヨーグルト
-
骨付き肉:鶏骨、牛骨
-
サプリメント:カルシウム補助剤やビタミンDサプリの過剰投与
ビタミンC過剰
体内でシュウ酸に変換されるため、サプリの過剰投与は避けること。犬さんは体内で合成可能なので、通常は不要です。
6. 予防
再発予防のポイントは以下です。
-
水分摂取の確保:十分な水分で尿量を増やします。
-
食事管理:リスク食材を控え、療法食で栄養バランスを管理します。
-
定期検査:尿検査・画像検査で再発を早期発見します。
-
尿pHモニタリング:中性〜弱酸性の維持します。
-
体重管理:肥満は結石リスク増加するので、適正体重を保つつことが重要です。
-
生活環境の整備:ストレスや運動不足の軽減を行います。
まとめ
犬さんのシュウ酸カルシウム尿石症は治療が難しく再発率も高い疾患ですが、原因理解と適切な管理により症状コントロールと再発予防が可能です。特に食事管理と水分摂取、定期検査は重要です。
ハグウェル動物総合病院 横浜鶴ヶ峰院の体制
セカンドオピニオン設置
下部尿路疾患の症状に対して迅速に対応し、必要な検査(血液検査・尿検査・レントゲン・超音波・CT検査など)を実施して、原因を特定し適切な治療を行います。
特に「頻尿」「血尿」「尿が出ない尿閉」などのケースでは、早期の処置が非常に重要です。
また、専門診療の腎泌尿器科(室 卓志獣医師)を設けているため、セカンドオピニオン、さらには重症化した下部尿路疾患や慢性腎臓病など、長期的なケアが必要なケースの受け入れを行っております。
横浜市から川崎・大和エリアまで、地域の皆さまの“かかりつけ”として、安心の獣医療をお届けします。
📢ご予約・ご相談はお気軽に!
LINE・お電話(045-442-4370)・受付(動物病院総合受付)にて承ります♪



