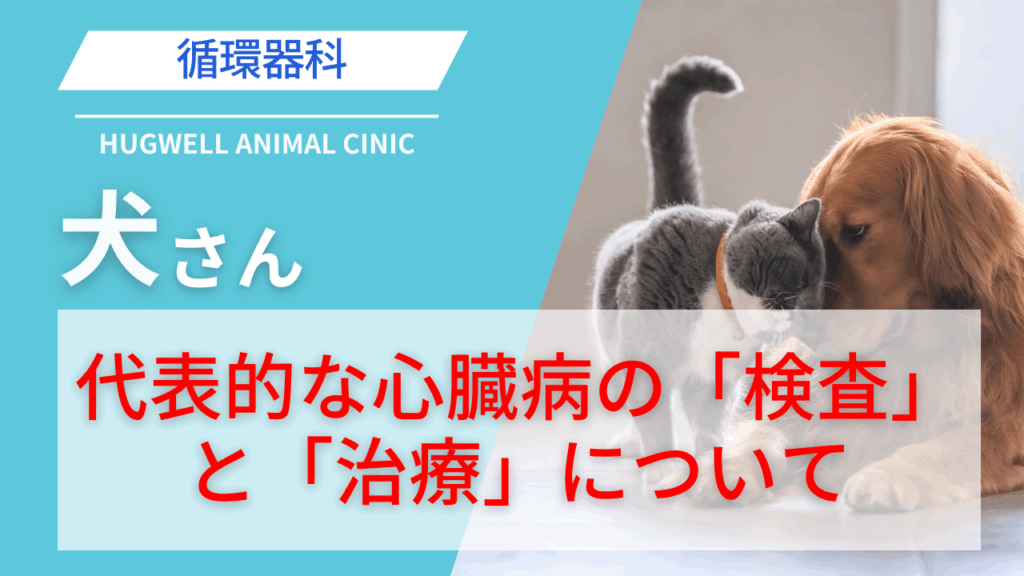
早期発見と適切なケアが、心臓の寿命を延ばします
心臓病は静かに進行することが多く、飼い主さんが異変に気づいたときには、すでに症状が進んでいることも少なくありません。だからこそ、正確な検査と早めの治療がとても大切になります。
ここでは、犬に多く見られる心臓病について、「どうやって診断するのか」「どんな治療があるのか」をご紹介します。
目次
 【循環器診療】森山 寛大
【循環器診療】森山 寛大
【担当科目】総合診療科・循環器科
 【循環器診療】佐藤 貴紀
【循環器診療】佐藤 貴紀
【担当科目】総合診療科・循環器科・栄養管理科
疫学エビデンス
犬さんの心臓病のうち、僧帽弁閉鎖不全症(MVD)と拡張型心筋症(DCM)が2大心臓病とされるのは、発生頻度によるものです。以下に、それぞ疾患についてエビデンスとともに解説します。
2大心臓病の割合(発生頻度)
参照文献:Borgarelli & Häggström, 2010
-
犬の心疾患のうち、およそ75〜80%が僧帽弁閉鎖不全症(MMVD)です
-
大型犬に多くみられる拡張型心筋症(DCM)は約10〜15%を占めます
-
これは米国・ヨーロッパの紹介症例ベースのデータに基づいています。
| 疾患名 | 発生割合 | 好発犬種 | 特徴 |
| 僧帽弁閉鎖不全症(MMVD) | 約75〜80% | 小型〜中型犬 |
加齢とともに進行する変性疾患
|
| 拡張型心筋症(DCM) | 約10〜15% | 大型犬 |
遺伝性が強く、進行が早い
|
| その他(先天性心疾患、心膜疾患など) | 約5〜10% | 雑多な犬種 |
PDA(動脈管開存症)、PS(肺動脈狭窄症)、心房中隔欠損など
|
僧帽弁閉鎖不全症(MMVD:粘液腫様僧帽弁疾患)
僧帽弁閉鎖不全症(そうぼうべんへいさふぜんしょう)は、犬の心臓病の中で最も多く見られる病気のひとつで、特に中高齢の小型犬に多く発生します。心臓には血液の逆流を防ぐための「弁」がいくつかありますが、僧帽弁は左心房と左心室の間に位置しています。この弁が加齢や変性によってうまく閉まらなくなると、血液が左心室から左心房へと逆流してしまい、心臓に負担がかかります。進行すると、心臓が拡大し、肺に水がたまる「肺水腫」などを引き起こし、咳や呼吸困難、元気消失などの症状が見られるようになります。早期に発見し、適切な内服薬による治療や生活管理を行うことで、病気の進行を遅らせ、快適な生活を長く保つことが可能です。
必要な検査
-
聴診:心雑音の有無をチェック(ほとんどのケースで発見のきっかけになります)
-
心臓超音波検査(エコー):逆流の有無や心臓の大きさを評価し、ステージを決定していきます。
-
胸部レントゲン:肺のうっ血、心臓の拡大を確認します
-
血圧測定/心電図:不整脈や血行動態の確認をします
-
BNP(心臓バイオマーカー)検査:心臓への負荷の程度を数値で把握します
検査における僧帽弁閉鎖不全症の重症度評価は、次の治療にとってとても重要です。特に、レントゲン検査、超音波検査により心臓の拡大や肺水腫の有無を診断し、ステージを決めていきます。
主な症状
| 症状 | 説明 |
| 乾いた咳 |
最もよく見られる初期症状。心拡大により気管が圧迫されるため
|
| 運動不耐性 |
散歩中に疲れやすくなり、途中で止まることがある
|
| 呼吸促迫・努力性呼吸 | 肺うっ血や軽度の肺水腫によって息が荒くなる |
| 夜間の咳 |
寝ているときにうっ血が起こりやすく、咳をして目覚める
|
| 失神 |
心拍出量の一時的低下や不整脈によって一過性の失神を起こす
|
| 食欲低下・元気消失 | 慢性的な心機能低下による全身状態の悪化 |
治療
-
強心薬(ピモベンダンなど):心臓のポンプの力をサポートし、適切な器官へ血液を送ります
-
利尿薬(フロセミドなど):肺うっ血や腹水を軽減します
-
ACE阻害薬:血管を広げ、心臓や血管への負担を減らす
-
食事管理・運動制限:塩分を控えた食事、過度な興奮や運動の回避を行います
- 外科的手術:ステージや病態により、心臓外科が適応になります
検査によりステージを診断し、適切な投薬を行います。心雑音が聞こえるからと投薬をむやみに始めても意味がありません。ステージや症状に合った投薬を行わなければ返って心臓の負担になることや、他の臓器への悪影響が出てしまうのです。
拡張型心筋症(DCM)
拡張型心筋症(DCM)は、心臓の筋肉が薄く伸びて拡張し、ポンプ機能が低下する疾患です。特に大型犬種(ドーベルマン、ボクサーなど)で多く見られます。心臓の収縮力が低下するため、全身への血液供給が不十分となり、元気消失、咳、呼吸困難、失神などの症状が見られます。進行すると肺水腫や腹水が生じ、命に関わる状態になることもあります。診断には心エコー検査が有用で、心室の拡張や収縮不全を確認します。
必要な検査
-
心エコー検査:心室の拡大や収縮力の低下を評価します
-
心電図:不整脈(特に心室性期外収縮)が見つかることが多いです
-
Holter心電図(24時間心電図):一過性の不整脈の検出に有効です
-
遺伝子検査(特定犬種):ドーベルマンやグレートデンで推奨していますが、ボクサーやせんとバーナードなどの大型犬、超大型犬は遺伝的関与が疑われています。
-
栄養学的問題:アメリカン・コッカー・スパニエルなどでは、栄養性の原因(タウリンとL?カルニチン不足)の関与が疑われています
確定診断には、心エコー検査が必要です。その他、心電図、レントゲン検査により投薬の方針を定めていきます。
主な症状
| 症状 | 説明 |
| 無気力・活動量の低下 |
初期から見られる。全身に酸素が届きにくくなるため
|
| 食欲不振・体重減少 | 心拍出量の低下により代謝全体が悪化する |
| 腹水・四肢浮腫 |
右心不全が進行すると、腹水や下肢の浮腫が見られることがある
|
| 呼吸困難・咳 | 左心不全による肺うっ血・肺水腫 |
| 失神・突然死 |
特にドーベルマンなどでは心室性不整脈が多く、致死的なリスクも高い
|
| 心雑音が乏しい |
心拡張と収縮低下が中心なので、聴診で異常を見つけにくいこともある
|
治療
-
強心薬:ピモベンダン、ジゴキシンなどで心収縮を補助
-
不整脈治療薬:ソタロール、アミオダロンなど(重度の不整脈がある場合)
-
利尿薬・ACE阻害薬:うっ血の改善と心臓の負担軽減
-
酸素吸入や点滴治療:急性症状時に対応
治療にはACE阻害薬、強心薬、利尿薬などが用いられ、心機能の維持と症状緩和を図ります。定期的な経過観察と内服管理が重要で、早期発見と継続的な治療がQOL維持の鍵となります。
| 疾患名 | 好発犬種 | 主なエビデンス | 予後 |
| 僧帽弁閉鎖不全症 | 小型犬(特にキャバリア) | EPIC試験・ACVIMガイドライン |
投薬で進行抑制可能
|
| 拡張型心筋症 | 大型犬(特にドーベルマン) | PROTECT試験・遺伝研究 |
突然死含め予後不良
|
最後に
犬に多く見られる心臓病である僧帽弁閉鎖不全症と拡張型心筋症は、症状や進行の仕方が異なるものの、いずれも早期発見・早期治療によって動物の生活の質(QOL)を大きく向上させることができます。日々の観察の中で「いつもと違う」と感じたら、迷わず動物病院にご相談ください。
ハグウェル動物総合病院の体制
セカンドオピニオン設置
今回の咳か、くしゃみか、逆くしゃみかの判断がわからないケースなど、的確な診断が必要な場合は、ハグウェル動物総合病院の循環器科をご予約ください。症状に対して迅速な対応を行います。
必要な検査として身体検査、血液検査、心エコー検査、レントゲン検査、心電図検査、血圧検査などを実施して、原因を特定し適切な治療を行います。
早期発見をしながら、どのタイミングで、どの投薬が望ましいのか、循環器認定医としっかり相談し決定することをお勧めいたします。
また、専門診療の循環器科(森山 寛大 獣医師・佐藤 貴紀 獣医師)を設けているため、セカンドオピニオンの受け入れも行っております。
横浜市から川崎・大和エリアまで、地域の皆さまの“かかりつけ”として、安心の獣医療をお届けします。
ご予約・ご相談はお気軽に!
LINE・お電話(045-442-4370)・受付(動物病院総合受付)にて承ります♪



