
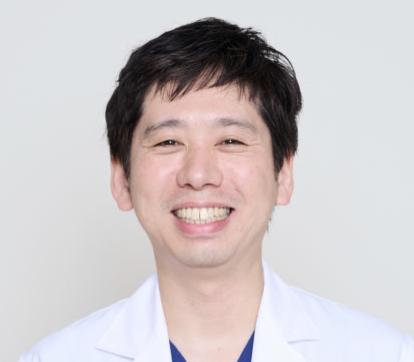
【腎泌尿器科診療】室 卓志 獣医師
【担当科目】総合診療科・腎泌尿器科・消化器科
目次
「腎臓」はどんな働き?
腎臓は、体の中の老廃物や余分な水分・ミネラルを尿として排出し、
体のバランス(電解質・血圧・水分量など)を整える“ろ過装置”のような臓器です。
この腎臓がダメージを受けると、体の老廃物が処理できなくなり、全身に影響が出ます。
慢性腎臓病ってどんな病気?
慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)は、腎臓の機能が少しずつ低下していく病気です。
腎臓は「体のろ過装置」として、老廃物や余分な水分を尿として排出する大切な臓器ですが、
一度機能が失われると再生することはほとんどありません。
初期のうちは目立った症状が出にくく、気づかないうちに進行してしまうことが多いのが特徴です。
特に猫では非常に多く、10歳を超える猫の約3頭に1頭が慢性腎臓病を抱えているとも言われています。
犬でも中〜高齢期になると発症リスクが高まります。
「急性腎臓病」と「慢性腎臓病」の違い
| 急性腎臓病(AKI) |
慢性腎臓病(CKD)
|
|
| 発症スピード | 突然(数時間〜数日) |
ゆっくり(数ヶ月〜数年)
|
| 原因 |
・脱水 |
・加齢による変化
・慢性炎症や高血圧
・遺伝的要因
・過去の急性腎障害の後遺症
|
| 症状 | ・急な食欲低下 ・嘔吐 ・下痢 ・尿が出ない/極端に少ない ・ぐったりする |
・徐々に食欲が落ちる
・水をよく飲む ・尿が多い ・体重減少、毛づやの低下 |
| 回復の可能性 | 原因を早く取り除けば、回復することもある |
腎臓の組織は再生しにくく、完治は難しい進行を遅らせる治療が中心
|
| 治療の目的 | 急速な腎機能障害の“回復” |
残った腎機能の“維持・保護”
|
| 治療の中心 | 入院での点滴治療・原因除去 |
食事療法・内服・定期検査・補液など継続ケア
|
主な症状
進行とともに、次のような変化が見られることがあります。
-
水をよく飲む・尿の量が増える(多飲多尿)
-
食欲が落ちる
-
体重が減る
-
嘔吐や口臭が強くなる
-
毛づやが悪くなる、元気がなくなる
こうしたサインは「年のせい」と思われがちですが、
実は腎臓の機能低下が関係しているケースも多いのです。
原因とリスク因子
慢性腎臓病の原因はさまざまですが、代表的なものには以下があります。
-
加齢による腎機能の低下
-
過去の急性腎障害(感染、薬物、中毒など)
-
遺伝的要因(特に猫の一部の純血種に多い)
-
歯周病や高血圧、心疾患などの慢性炎症
高齢動物さんだけでなく、若い時期からの生活習慣や栄養管理も発症リスクに影響します。
診断とステージ分類
血液検査や尿検査で腎臓のろ過能力(クレアチニン、SDMAなど)や尿の濃縮力を評価します。
国際的には「IRIS分類(ステージ1〜4)」に基づき、進行度を判断します。
ステージが進むほど腎機能が低下し、治療や食事の管理もより厳密に行う必要があります。
| ステージ | 腎機能の状態 | 主な血液検査値(目安) | よく見られる症状 | ケアのポイント |
| ステージ1 | 腎機能のごく軽い低下(早期・無症状) |
高窒素血症なし クレアチニン: |
ほとんど症状なし |
定期的な血液・尿検査で早期発見。血圧や尿比重をチェックし、原因を特定。
|
| ステージ2 | 軽度の腎機能低下 |
軽度の高窒素血症 クレアチニン: |
飲水量の増加、尿量の増加、体重減少など |
腎臓用食の導入を検討。定期的なモニタリングで進行抑制。
|
| ステージ3 | 中等度の腎機能低下 |
中等度の高窒素血症 クレアチニン: |
食欲不振、嘔吐、脱水、口臭、元気消失など |
食事療法+内服治療(血圧・リン・尿毒素対策)。皮下補液を併用することも。
|
| ステージ4 | 高度な腎機能低下(末期) |
重度の高窒素血症 クレアチニン: |
食欲廃絶、重度の嘔吐、貧血、意識低下など |
集中的な支持療法(輸液・食欲管理・緩和ケア)。生活の質(QOL)の維持を最優先に。
|
治療とケアの基本
慢性腎臓病は完治が難しい病気ですが、早期発見と継続的なケアで進行を遅らせることができます。
-
食事療法(腎臓サポート食)
たんぱく質・リン・ナトリウムを適切に制限し、腎臓への負担を減らします。
嗜好性を保ちながら、食べられる工夫も大切です。 -
内服治療・補液
血圧のコントロールや、尿毒素の蓄積を抑える薬を使うことがあります。
必要に応じて皮下補液で水分をサポートします。 -
定期的なモニタリング
血液検査・尿検査・体重・食欲・飲水量をこまめにチェックし、
状態に合わせて治療を調整していきます。
予防と早期発見のために
-
年1〜2回の健康診断で腎機能(特にSDMA)をチェック
-
シニア期(7歳以上)では半年に1回の血液・尿検査を推奨
-
日常の飲水量や排尿の変化に敏感に気づくこと
腎臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれるほど、症状が出る頃にはかなり進行しています。
だからこそ、早期発見=健康寿命の鍵になります。
まとめ
慢性腎臓病は「治す」より「進行を遅らせる」ことが治療のゴールです。
日々の観察と定期検診、そして飼い主さんと動物病院が二人三脚で取り組むことで、
より長く、快適に暮らすことが可能になります。
セカンドオピニオン設置
下部尿路疾患の症状に対して迅速に対応し、必要な検査(血液検査・尿検査・レントゲン・超音波・CT検査など)を実施して、原因を特定し適切な治療を行います。
特に「頻尿」「血尿」「尿が出ない尿閉」などのケースでは、早期の処置が非常に重要です。
また、専門診療の腎泌尿器科(室 卓志獣医師)を設けているため、セカンドオピニオン、さらには重症化した下部尿路疾患や慢性腎臓病など、長期的なケアが必要なケースの受け入れを行っております。
横浜市から川崎・大和エリアまで、地域の皆さまの“かかりつけ”として、安心の獣医療をお届けします。
📢ご予約・ご相談はお気軽に!
LINE・お電話(045-442-4370)・受付(動物病院総合受付)にて承ります♪

