目次
~慢性腸症の原因と最新の治療アプローチ~
「もう1週間以上、ずっと軟便が続いている」「食欲はあるのに、下痢だけが治らない」――。
こうした訴えで来院される飼い主様は少なくありません。特に、元気や食欲が保たれている場合、つい様子を見てしまいがちですが、実は“慢性腸症(chronic enteropathy)”という消化器の疾患が背景にあることがあります。
今回は、「治らない下痢」=慢性腸症の可能性と、近年注目されている治療法について、獣医師の視点からご紹介します。

慢性腸症とは?
慢性腸症(CE)とは、3週間以上続く下痢・軟便・嘔吐・体重減少などの慢性的な消化器症状を呈する疾患群のことです。大きくは以下のように分類されます:
慢性腸症の分類
| 分類 | 特徴 |
| 食事反応性腸症(FRE) |
特定の食事(加水分解食や除去食)への変更で症状が改善
|
| 抗菌薬反応性腸症(ARE) |
抗菌薬(主にメトロニダゾールやタイロシン)に反応
|
| 免疫介在性腸症(IRE) |
ステロイドや免疫抑制剤に反応
|
| 非反応性腸症(NRE) |
上記の治療で反応しないもの
|
なぜ起こる?~原因の多様性~
慢性腸症の正確な発症メカニズムはまだ完全には解明されていませんが、「腸内環境の破綻」「免疫の過剰反応」「バリア機能の異常」などが関与していると考えられています。
原因
- 食物アレルギー/不耐性(牛肉、小麦、乳製品など)
- 腸内細菌叢の異常(ディスバイオーシス)
- 遺伝的素因(特にジャーマンシェパードやヨークシャーテリアなど)
- 環境ストレスや慢性的な炎症など
どうやって診断するのか?
慢性腸症の診断は「除外診断」が基本です。他の病気(寄生虫感染、膵外分泌不全、ガンなど)を排除し、食事・抗菌薬・免疫抑制剤への反応性を見ながら分類していきます。
検査の一例:
- 便検査:寄生虫や感染症の確認
- 血液検査:CRP、アルブミン、ビタミンB12、葉酸、炎症や吸収障害の評価
- 超音波検査:腸の壁の厚みやリンパ節の確認、膵炎の有無など消化器を網羅的に確認
- 食事トライアル:加水分解タンパク質や新奇タンパク質を試す除去食療法
- 内視鏡検査・生検:炎症のタイプや重症度、ガンとの鑑別
慢性腸症と炎症性腸疾患(IBD)の違い
| 項目 | 慢性腸症(CE) |
炎症性腸疾患(IBD)
|
| 定義 | 3週間以上続く消化器症状(下痢・嘔吐・体重減少)を示す慢性疾患群の総称 |
CEのうち組織学的にリンパ球・形質細胞性の炎症が確認された状態
|
| 診断方法 | 除外診断+治療反応性に基づく分類(FRE/ARE/IREなど) |
内視鏡または開腹手術による腸粘膜の生検で確定
|
| 病理学的特徴 | 多様(病理が未確認でも含まれる) |
腸粘膜における慢性炎症細胞(リンパ球・形質細胞)浸潤
|
| 範囲 | より広い概念(IBDを含む) |
慢性腸症の一部カテゴリ
|
| 原因の特定 | 治療への反応で分類(食事/抗菌薬/免疫抑制剤) |
原因は不明だが免疫異常の関与が強いとされる
|
| 治療のアプローチ | 段階的な治療反応性試験(例:除去食 → (抗菌薬) → 免疫抑制)(ステップアップアプローチ、ステップダウンアプローチ) |
主に免疫抑制剤(ステロイド、シクロスポリンなど)を使用
|
| 病態の位置づけ | 臨床的な包括的診断名 |
組織学的な診断名
|
最新の治療アプローチ
慢性腸症は「一つの治療ですべて解決」という単純な病気ではありません。以下のステップアプローチ(治療強度を徐々に上げていく方法)が近年主流です。
① 除去食・加水分解食の導入
最初に試すべきは「食事療法」。食物アレルギーが関与するFREが最も多いため、加水分解タンパク質フードや新奇タンパク質フードを最低2週間〜4週間継続します。
② 抗菌薬療法
改善が見られなければ、抗菌薬(メトロニダゾールやタイロシン)を使い、腸内細菌のバランス改善を図ります。
③ ステロイド・免疫抑制剤の投与
それでも反応がなければ、免疫介在性を疑いプレドニゾロンやシクロスポリンなどの免疫抑制療法へと進みます。
上記治療で改善がみられない場合は、リンパ腫(ガン)との鑑別を目的に内視鏡検査が強く推奨されます。
注目の“マイクロバイオーム療法”とプロバイオティクス
最近注目されているのが、腸内細菌叢(マイクロバイオーム)を整える新しい治療法です。
- プロバイオティクス・プレバイオティクスの併用
・プロバイオティクス:乳酸菌やビフィズス菌など
・プレバイオティクス:オリゴ糖や食物繊維など
- 食物繊維強化食:高発酵性繊維など
- FMT(糞便微生物移植):健康な犬の糞便を用いた細菌叢のリセット法
こうした治療は薬に頼らず自然な方法で腸内環境を整えるアプローチとして、特に再発を繰り返す犬に対して有望視されています。
さいごに:飼い主としてできること
慢性腸症は完治が難しいこともありますが、適切な食事管理と治療でコントロールが可能です。
「いつもの下痢だから大丈夫」と見過ごさず、3週間以上続く場合は必ず動物病院へ相談を。早期の診断と対策で、愛犬の生活の質は大きく改善します。
【監修】
獣医師 室 卓志(消化器科)
動物の“お腹”の悩み、いつでもご相談ください。
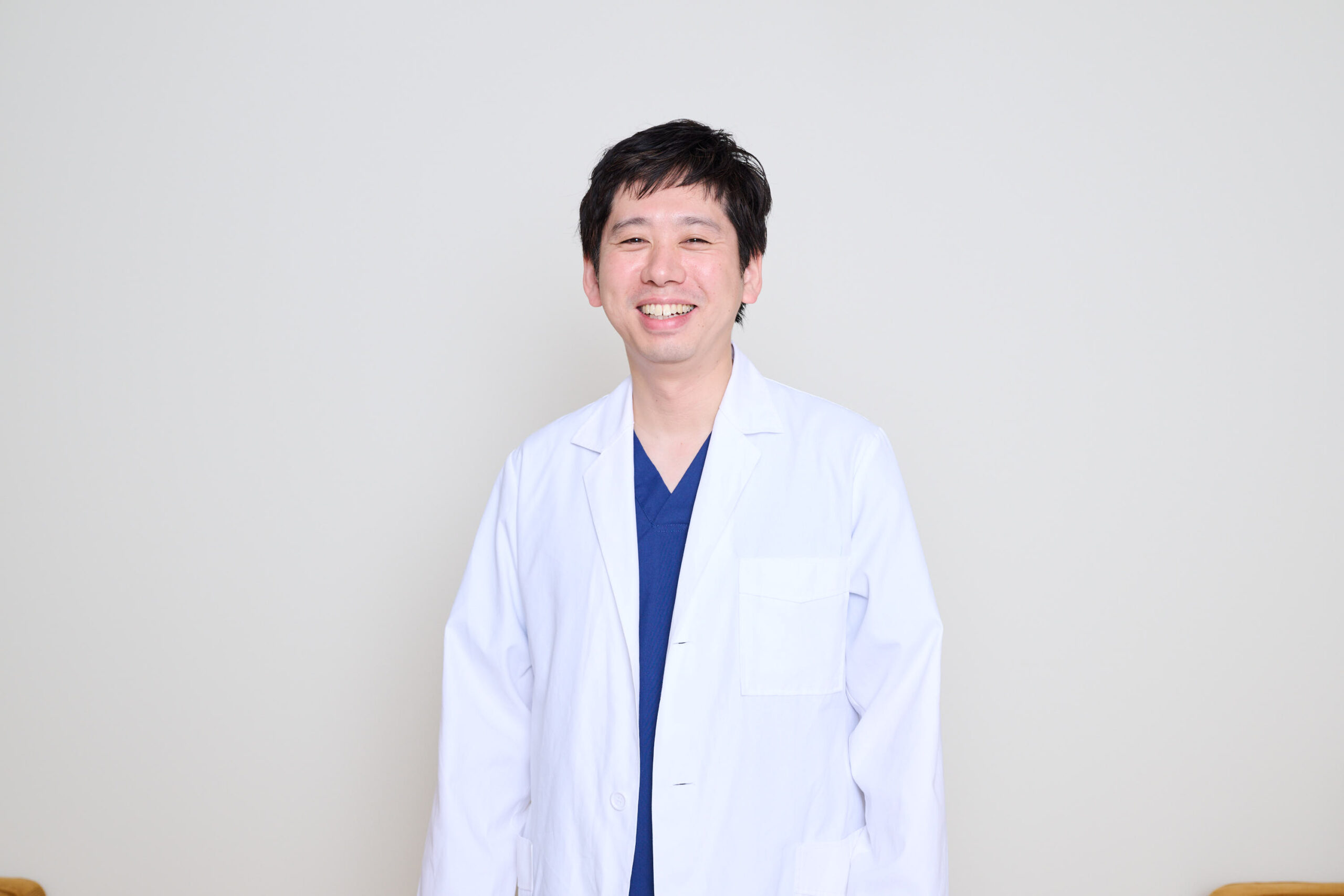
ハグウェル動物総合病院 横浜鶴ヶ峰院の体制
セカンドオピニオン設置
下痢の症状に対して迅速に対応し、必要な検査(便検査・血液検査・レントゲン・超音波・消化管造影検査・内視鏡検査など)を実施して、原因を特定し適切な治療を行います。
特に「急な下痢」「血便」「異物誤食が疑われる」などのケースでは、早期の処置が非常に重要です。
また、専門診療の消化器科(室 卓志獣医師)を設けているため、セカンドオピニオンや長期の下痢、さらには繰り返す消化器症状(嘔吐や下痢)など、治りが悪い症状の受け入れを行っております。
横浜市から川崎・大和エリアまで、地域の皆さまの“かかりつけ”として、安心の獣医療をお届けします。
📢ご予約・ご相談はお気軽に!
LINE・お電話(045-442-4370)・受付(動物病院総合受付)にて承ります♪



